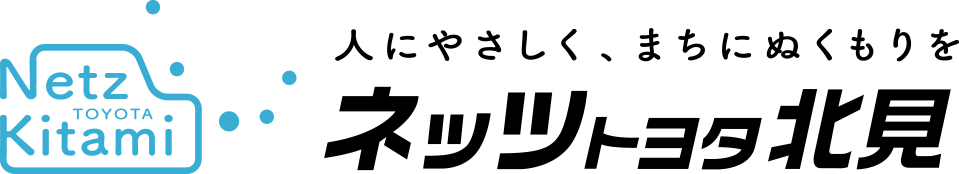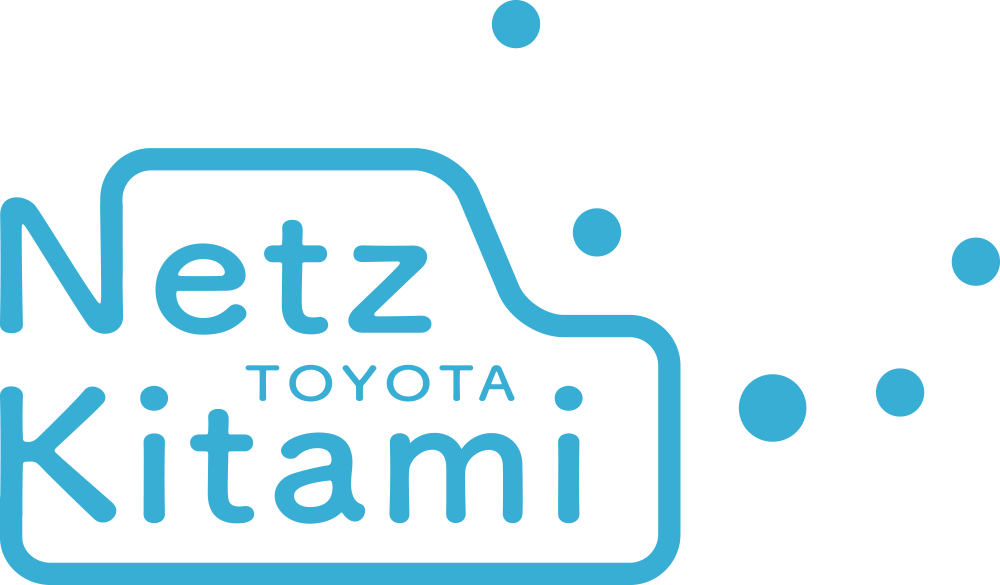TOPページ » ネッツ北見だからできること » 吉田知那美コラム Vol.19
吉田知那美のコラム Vol.19
Yoshida Chinami Column VOL.1
HUGの話
1年前の5月、父が病に倒れ、6月の初旬に旭川の病院に入院した。
その頃から私は夜になると嗚咽するように泣くようになってしまい、うまく眠れなくなった。
父の病名を聞き、お医者さんの説明を聞き、聞いたこともなかったその病気を調べ、セカンドオピニオンとして別のお医者さんにも説明を聞き、ようやく父に突然言い渡されたあまりにも短い余命は、嘘じゃないことがわかった。
わかったけど、簡単に受け止められるものではなかった。
先週まで一緒にお酒を飲んで笑ってた父が、来年はこの世にいないなんてことを、理解はできても受け止められなかった。
日中、元気に笑って過ごそうと頑張れば頑張るほど、夜になると「ちち死なないで」と叫びながら泣いた。(吉田家では父のことをちちと呼ぶ)
隣で嗚咽して息ができなくなっている私をすっぽりと丸ごと包み込むようにしながら、夫はずっと背中をさすってくれていた。
「吸って、吐いて。」と息ができるように促してくれるだけで、それ以外は何も言わずにずっと背中を包み込むようにハグをしてさすってくれていた。
そうしたら大体いつもいつの間にか寝ていて、気がついたら朝になっていた。朝になると、痛みを感じるほど泣き腫らしたまぶたにうんざりしながら、どうにか起きていた。大泣きした次の日は、もれなく頭も痛かったし、寝たはずでも朝から疲れていた。

夫がいない日の父との面会は、一人でどうにかしなきゃいけなかった。
面会後はいつも病院の一階にあるスターバックスのカウンター席の角で、今日の父の様子と何を話したかを一語一句、赤いノートに書き留めた。新婚旅行の時、ミラノで買った高級ノート。ミラノ・コルティナ五輪までの気持ちを記録するカーリングノートにしようと思って買ったけど、父との会話の記録ノートにした。
ノートに記録し終えたら、母に電話して父の様子を伝えた。電話を切ったら車に戻って泣いた。
ひとりで泣き止むことができたら、そのまま運転して北見に帰った。
でも、泣き止むことができなかったり、運転ができないと判断したときは、帰るのを諦めてその場でホテルを取って旭川に泊まることにしていた。
運転免許取得の際や、免許更新の際などにも勉強したが、体調や心の調子が悪い時は運転を避けること。
それはわたし自身が父の面会のために旭川へ通っている時に肝に銘じていた約束事だった。
旭川に泊まると決めても、夜ひとりでホテルの部屋にいるのも嫌だった。疲れて寝れるようにジムに行ってトレーニングをしたりした。
それでも寝れない時は、しかたなしに旭川の街を散歩した。
心が元気な時には呼ばれてるような気持ちになる赤提灯だけど、その時はギンギラに光る提灯が灯る居酒屋へは足が向かなかった。
そんな時、ポツンと小さな光が灯ってるお店を見つけて、あそこなら入れそうと覗いてみる。
そこは、クラフトビールのお店だった。
お店に入ると7種類くらいのタップが用意されていた。一階は立ち飲みスタイルのカウンターとテーブルが2つ。2階は座れるとのことだったので2階席を使わせてもらった。誰もいなかった。
注文したビールを持ってきてくれた店員さんはオシャレなタトゥーに身を包んだ男性だった。
その店員さんが、「もしかしてロコ・ソラーレの方ですか?」と声をかけてくれた。
「はい、そうです。姉の方です。」とお決まりの定型文で答えると「やっぱり。応援してます。」とだけ伝えてくれた。

頼んだビールはちょうど良い温度に冷えていて美味しかったが、一口飲んで空きっ腹だったことに気がついた。アルコール度数もまぁまぁ高いIPAを頼んだのでゆっくり飲んだ。ビールが減っていくのと同じくらいのペースで、少しずつ気持ちが落ち着いてきて居心地が良かった。
閉店時間間際だったので一杯飲んで早めに帰ろうと思っていたら、「まだ片付けに時間もかかるからゆっくり飲んでてください」とわざわざ伝えに来てくれた。
お言葉に甘えてゆっくりさせてもらっていると一階から、マーヴィンゲイの曲が流れてきた。
マーヴィンゲイは父が好きだったアーティストで、わたしも大好きで小さいころからよく家でかかっていたし、今も聞いてる。父と2人でお酒を飲む時は彼のレコードを選んでかけることも多かった。
我が家の第二の家と言っても過言ではない、地元にある喫茶店しゃべりたいでもよくかかっている曲がある。
その曲が、初めて入った旭川のクラフトビール屋さんでかかっていた。
ビールグラスを持っておもむろに一階に降り、好きな曲がかかってるから一階で飲んでもいいか聞いたら、快く迎えてくれた。
その日からわたしは、そのお店のオーナーのやっち、その奥さんでお店番をしているあいちゃん、そしてロコ・ソラーレの方?と話しかけてくれた店員のかずくんと友達になった。
ひとりで泣き止めなくて北見に帰れなくなった日や、ハグをして背中をさすってくれる夫がいない日には、そのお店に行くようになった。
そのお店の名前は、HUG(ハグ)という。
その当時のわたしにとってHUGは、名前の通りのお店だった。
やっちもあいちゃんもかずくんも、お客さんを包み込むようにいつも温かで穏やかな「いらっしゃいませ」で迎えてくれる。
心地の良い音楽と、美味しいビールを用意して待っていてくれる。
わたしはHUGにとび込むように入店し、HUGで背中をさすってもらうようにリラックスする時間を過ごし、そしてホテルに帰りひとりで朝までちゃんと寝た。
父が亡くなってからも、わたしはたまにHUGに行く。HUGは心地が良いし、何よりとても感謝してる。
やっち、あいちゃん、かずくん、ありがとう!!ぎゅ!(big hug!)